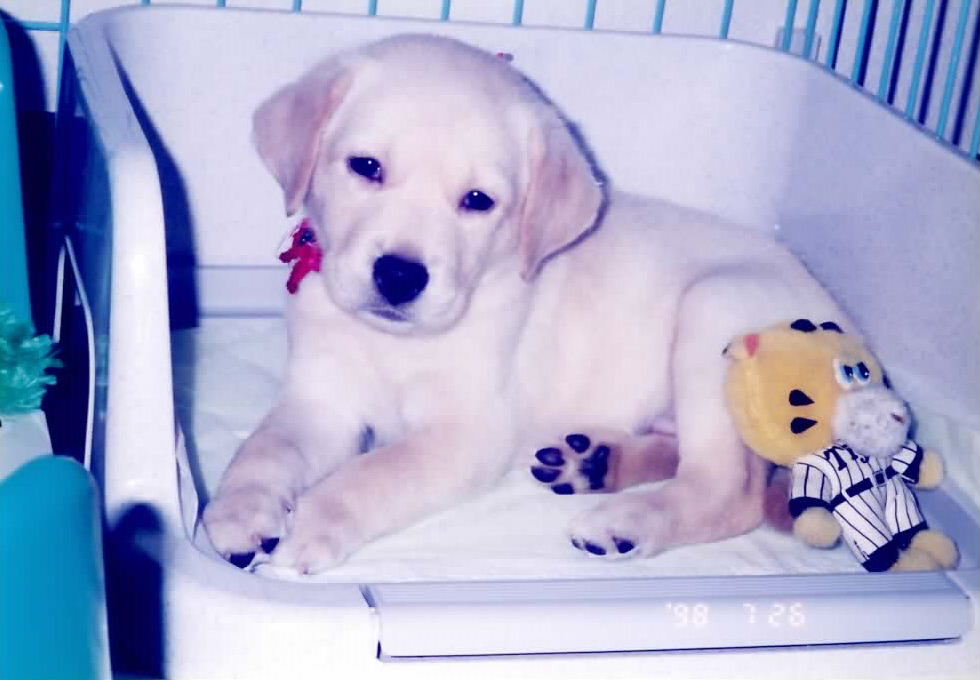「急におもらしするようになってしまった…」そんな時、心配で胸がいっぱいになりますよね。
この記事では、実際の飼い主さんの声や体験談も交えながら、愛犬の失禁トラブルをやさしく乗り越える方法をご紹介します。
突然の失禁、どうしたらいいの?
ある日、寝ていた愛犬のベッドに小さなシミを見つけて「えっ」と驚いたことはありませんか?
私も以前、10歳を迎えたラブラドールの「もも」が急に失禁したとき、最初はパニックになってしまいました。
でも獣医師から「それは年齢による自然な変化」と説明を受け、安心したのを覚えています。
失禁は、単なる「しつけの失敗」ではなく、体調や心のバランスが崩れているサイン。
叱るよりも、まずは原因を知って寄り添うことが大切です。
- 失禁の頻度:1回だけか、毎日続くか
- 尿の状態:濁りや血、においの変化
- 体調の変化:元気・食欲・歩き方など
- 最近の環境:引っ越し、天候、ストレス要因
愛犬が失禁する理由とは?
① 加齢や体の変化によるもの
シニア犬になると、膀胱や尿道の筋肉が少しずつ弱り、尿を我慢する力が低下してきます。
特にメス犬は、避妊手術後にホルモンバランスが変わり、尿漏れを起こしやすくなることも。
🐶飼い主さんの声:
「うちの柴犬・はなは12歳を過ぎた頃から、寝ている間に少し漏れることが増えました。最初はショックでしたが、ペットシーツを多めに敷いておくことで、本人も私も安心して過ごせています。」
② ストレスや環境の変化
引っ越しや家族構成の変化、雷・花火などの大きな音が続くと、犬は強いストレスを感じます。
安心できる環境が崩れると、排尿コントロールが一時的に乱れることがあります。
🐾体験談:
「新しい家に引っ越した初日におもらし。怒らずに優しくなでながら“ここが新しいおうちだよ”と声をかけたら、数日で落ち着きました。」
③ 病気が原因のケース
尿漏れが頻繁に続く場合や、血尿・痛がる様子がある場合は、病気の可能性も考えられます。
膀胱炎、尿路感染、腎臓病、クッシング症候群、神経疾患など、多くの原因が隠れていることがあります。
特にシニア期には、「多飲多尿(たくさん飲んでたくさん出す)」というサインも見逃せません。
| 主な原因 | 特徴 | 家庭での初期対応 |
|---|---|---|
| 加齢・筋力低下 | 寝起き・興奮時に漏れる | トイレ誘導を増やす・滑りにくいマット設置 |
| ストレス | 来客後や雷の後に漏らす | 落ち着けるスペースを確保・声かけで安心 |
| 膀胱炎・感染症 | 頻尿・血尿・臭い | 早めに動物病院へ・採尿できれば持参 |
| 結石・神経疾患 | 痛み・歩行異常 | 無理に動かさず受診・診察時に行動記録を提示 |
愛犬の失禁を改善するためのステップ
① トイレトレーニングを見直す
失禁が増えたとき、まずはトイレ環境を再確認してみましょう。
床が滑りやすい、場所が変わった、匂いが強いなど、小さな違いが原因のこともあります。
成功したときにはすぐに褒めて、ごほうびをあげるのがポイント。
叱らずに「できたね!」を積み重ねていくことで、自信が戻ってきます。
🐾体験談:
「老犬のトレーニングは根気がいりますが、焦らず“失敗しても大丈夫”の気持ちで続けたら、1か月ほどで落ち着きました。」
② 獣医師に相談するタイミング
次のような場合は、できるだけ早めに受診しましょう。
- 尿の色がピンクや赤い
- 強いにおい・濁りがある
- 何度もトイレに行くが少量しか出ない
- 背中やお腹を触ると嫌がる
診察時には、尿の写真や排尿回数のメモがあるとスムーズです。
③ 生活環境の見直し
- 床対策:滑り防止マットで安心して歩けるように
- 段差の軽減:スロープを使って移動の負担を減らす
- 温度管理:冷えは膀胱炎の原因にも。冬は暖かい寝床を
こうした小さな工夫が、愛犬の失禁トラブルを大きく減らしてくれます。
失禁を防ぐための日常習慣
① 定期的な排尿タイムを作る
「朝」「食後」「寝る前」など、毎日決まった時間にトイレへ誘導してあげましょう。
タイミングが一定になると、体のリズムが整い、失禁が減ることがあります。
② 安心できる空間づくり
人通りが多い場所にトイレを置くと落ち着けません。
静かで薄暗い場所に設置し、雷や来客時はカーテンを閉めたりBGMを流して安心感を作りましょう。
③ 信頼関係を深める習慣
叱らずに、優しく見守る姿勢が何よりの安心。
失敗しても「いい子だね」と声をかけて、ストレスを溜めないことが回復への第一歩です。
病気が疑われる場合の対処法
① 診断と検査の流れ
動物病院では、問診→尿検査→血液検査→超音波検査の順で調べます。
尿を持参する際は、清潔な容器に入れて冷蔵保存し、できるだけ早く提出しましょう。
② 治療とケアの例
- 膀胱炎:抗生剤と水分摂取の増加で改善するケースが多い
- ホルモン異常:薬によるホルモン補充や食事療法
- 神経疾患:リハビリ・サプリメント・生活サポートの併用
🐶実例:
「うちのダックスは椎間板ヘルニアが原因で尿漏れがありました。先生の指導で、リハビリと体重管理を続けたら、半年後にはほぼ改善しました。」
③ フォローアップの重要性
治療後もしばらくは観察が必要です。再発を防ぐためには、尿のにおいや色を日々チェックしておくのがポイント。
カレンダーに排尿時間を書き込むだけでも、体調変化に気づきやすくなります。
愛犬にやさしい排尿管理アイデア
① ペット用の防水マット・オムツを活用
寝る場所や留守番スペースには、防水マットや吸収性の高いペットシーツを敷きましょう。
最近はデザイン性が高く洗えるタイプもあり、インテリアを損なわず快適に使えます。
② 飼い主のサポートが安心を生む
愛犬が失敗しても、「大丈夫、次はうまくいくよ」と声をかけてあげてください。
飼い主のトーンや笑顔は、犬にとって最高の薬です。
ストレスを感じるほど症状が悪化するケースもあるため、落ち着いた雰囲気を心がけましょう。
③ 短期対策と長期ケアの両立
- 短期:マット・オムツ・頻回のトイレ誘導・消臭清掃
- 長期:筋力維持のための軽い運動・バランスのとれた食事・定期検診
長く寄り添うために、日々のケアを無理なく続けていくことが大切です。
まとめ:叱るより、寄り添う気持ちを
愛犬の失禁は、年齢や病気、心の不安など、いくつもの要因が重なって起こるものです。
大切なのは、焦らず・責めず・一緒に乗り越えること。
「今日も頑張ったね」と優しく声をかけながら、安心できる時間を増やしていきましょう。
飼い主の愛情は、どんな薬にも勝る力になります。
ライター紹介 Writer introduction
いずもいぬ
管理人:いずもいぬ(五十代前半) 家 族:子供1人とワンコの4人家族 居住地:大阪の出身で東京生活を踏まえ、現在は山陰で田舎暮らしをしています。 犬の健康管理や躾について、愛犬のラブラドールレトリバーとの経験を交えてご紹介しているホームページになります。