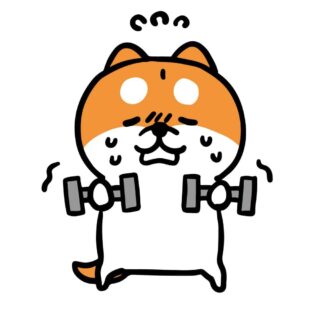愛犬にカプッと噛まれて、「えっ、なんで?」「私のこと嫌いになったのかな…」と不安になったことはありませんか。
実は、犬が噛む行動にはいくつもの理由があり、そのすべてが“悪い行動”というわけではありません。
この記事では、犬が噛む理由を9つのパターンに分けて、女性や初心者の飼い主さんにも分かりやすく解説していきます。
噛む行動の背景を知ることで、愛犬との付き合い方がきっと優しく変わっていきますよ。
1. 犬が噛む行動…まずは「理由」を知ることから
犬が噛むのは“問題行動”だけではない
「噛む=悪いこと」というイメージを持たれがちですが、犬の世界では必ずしもそうとは限りません。
甘えたいとき、遊びたいとき、逆に怖いときやイヤなときなど、犬はさまざまな気持ちを“口”を通して表現します。
大切なのは、「噛んだ」という結果だけでなく、その前にどんな気持ちがあったのかを知ろうとすることです。
犬が噛みたくなるメカニズム(本能と気持ち)
犬はもともと、口を使って世界を確かめる動物です。
子犬の頃は特に、歯がむずむずしたり、好奇心から何でも口に入れたりしますよね。
さらに、恐怖や不安を感じたときには、自分を守るために噛んでしまうこともあります。
つまり、「本能」+「そのときの気持ち」が重なって、噛む行動として出てくるのです。
噛む理由は1つじゃない!9つに分けて考える
同じ「噛む」という行動でも、愛情表現のときと、怖くて噛んでしまったときでは、対処法が大きく変わります。
ここからは、犬が噛む理由を9つのパターンに分けて、分かりやすく見ていきましょう。
2. 犬が噛む9つの理由:パターン別に徹底解説
① 愛情表現としての「甘噛み」
飼い主さんの手や指を軽くカプカプ噛むのは、甘えやスキンシップの一種であることが多いです。
子犬同士がじゃれ合うように、「一緒に遊びたいな」「うれしいな」という気持ちで噛んでいる場合もあります。
② 遊びの一部としての噛みつき
ボールやおもちゃを追いかけているうちに、手まで噛んでしまうことも。
この場合は、遊びのテンションが上がりすぎて、力加減が分からなくなっていることが多いです。
「手はおもちゃじゃないよ」と教えてあげることが大切です。
③ 恐怖や不安からくる防衛反応
叱られたときや、急に大きな音がしたとき、知らない人に触られたときなど、犬が「怖い」「これ以上近づかないで」と感じたとき、防衛本能で噛んでしまうことがあります。
この場合、犬は攻撃をしたいのではなく、「それ以上やめてほしい」というSOSを出しています。
④ 誤認から生じる噛みつき
飼い主さんの手が、おもちゃやおやつと一緒に動いているとき、勢いあまって手まで噛んでしまうことがあります。
犬からすると、「手」なのか「おもちゃ」なのか区別がつきにくいこともあるのです。
⑤ 痛みや体調不良による噛みつき
触られた場所に痛みがあるとき、いつも優しい子でも噛んでしまうことがあります。
足やお腹、口の中など、痛い部分に触れられると、「やめて!」というサインとして噛んでしまうことも。
急に噛むようになったときは、体調やケガの可能性も考えてあげましょう。
⑥ ストレス・退屈・運動不足
運動が足りていなかったり、ひとりの時間が多かったりすると、フラストレーションがたまり、噛む行動として表れることがあります。
クッションや家具を噛んでしまうのも、このパターンのひとつです。
⑦ 子犬の歯の生え変わりによるムズムズ
子犬の時期は歯が生え変わるため、歯ぐきがむずむずして何かを噛まずにはいられないことも。
この時期に「噛んでいいもの」と「噛んではいけないもの」をきちんと教えてあげることが大事です。
⑧ 物を守る行動(リソースガーディング)
フードボウルやお気に入りのおもちゃ、ベッドなどに近づくと唸ったり噛もうとしたりする場合、「これは私のものだから取らないで!」という気持ちから噛んでいることがあります。
これをリソースガーディング(資源の防衛行動)と言います。
⑨ 社会化不足による人の手への警戒
子犬の頃に、人や他の犬と触れ合う機会が少なかった場合、人の手や急な動きに強い警戒心を持つことがあります。
その結果、「触られたくない」という気持ちから噛んでしまうこともあります。
3. 噛む行動を正しく理解するためのポイント
犬のボディランゲージを読み取る
犬は言葉を話せませんが、耳・しっぽ・目線・姿勢など全身で気持ちを表現しています。
しっぽを巻き込んでいたり、耳が後ろに倒れていたり、目をそらしているときは、不安や緊張を感じているサインかもしれません。
噛む前には必ず何かしらのサインがある
多くの場合、犬は何の前触れもなくいきなり噛むわけではありません。
「唸る」「体を固くする」「後ずさりする」など、小さなサインが出ていることがほとんどです。
そのサインに気づいてあげることが、噛まれる前に対処する第一歩になります。
原因によって対処法はまったく変わる
甘噛みなのか、恐怖からなのか、痛みからなのか…。
同じ「噛む」という行動でも、理由が違えば、やるべき対応も変わります。
大切なのは、「なぜ噛んだのか?」を考える習慣を持つことです。
4. 犬の噛みつき対策:タイプ別のしつけ方法
甘噛み・遊び噛みへの対処法
遊びの延長で噛んでしまう場合は、手ではなくおもちゃを噛ませるように誘導しましょう。
噛まれたときに大きな声で騒ぐと、逆に「もっとやっていいんだ!」と興奮してしまうこともあるので、落ち着いて手をそっと引き、「おもちゃにしようね」と切り替えることが大切です。
恐怖や不安から噛む場合の対応
怖がっている犬を無理に触ったり、叱ったりすると、噛みつきが悪化することがあります。
この場合は、距離をとって安心できる環境をつくり、ゆっくり時間をかけて慣らしていくことが必要です。
誤認からの噛みつきは「手をおもちゃにしない」ことから
日頃から、手で激しくじゃれ合う遊びは控え、必ずおもちゃを介して遊びましょう。
手=噛んでいいもの、という勘違いをさせないことがポイントです。
物を守って噛むときの対処(リソースガーディング)
無理に取り上げるのではなく、交換ルールを教えていきます。
「もっと良いものと交換してもらえる」と学ぶと、守る必要がなくなり、落ち着きやすくなります。
社会化トレーニングの大切さ
子犬の頃から、いろいろな人・犬・環境に少しずつ慣れさせてあげることで、不安から噛んでしまうリスクを減らすことができます。
成犬になってからでも、ゆっくり時間をかけて、安心できる経験を積ませてあげることが大切です。
5. 専門家に相談すべきサインとは?
危険な噛み方のサイン
次のような様子が見られる場合は、早めに専門家への相談をおすすめします。
- 唸りながら歯をむき出しにすることが増えた
- 噛んだあとも興奮がおさまらない
- 家族や他の犬を繰り返し本気で噛もうとする
獣医師・トレーナー・行動診療科の活用
痛みや病気が原因で噛んでいる場合もあるため、まずは獣医師に相談するのが安心です。
行動やしつけの問題が大きそうなときは、ドッグトレーナーや、専門の動物行動診療科に相談する選択肢もあります。
6. 噛む行動を減らすためにできる日常ケア
運動量とストレス発散
散歩や遊びが足りていないと、エネルギーが余って噛む行動につながることがあります。
年齢や体格に合った運動を取り入れ、心身ともにすっきりさせてあげましょう。
噛んで良いものを用意してあげる
デンタルトイやガムなど、「噛んでOKなおもちゃ」を用意することで、家具や手を噛む代わりに、そちらでスッキリしてくれることも多いです。
7. 愛犬とのコミュニケーションの質を高める
「叱る」よりも「理由を理解する」
噛んだからといって、一方的に叱ってしまうと、犬はますます不安になってしまうことがあります。
まずは「この子は何を伝えたかったんだろう?」と、一歩引いて考えてみることが大切です。
安心して甘えられる関係づくり
日頃から、優しく声をかけたり、落ち着いたスキンシップの時間をとることで、犬は「この人のそばは安心できる」と感じやすくなります。
安心感は、噛む行動の減少にもつながっていきます。
信頼関係が噛む原因解消の第一歩
信頼関係が育ってくると、犬は「この人なら大丈夫」と思えるようになり、不安や恐怖からの噛みつきは少しずつ減っていきます。
焦らず、ゆっくりと時間をかけて絆を深めていきましょう。
8. まとめ:噛む行動の裏側にある「気持ち」を見つめてみよう
犬の噛む行動には必ず理由がある
愛情表現、遊び、恐怖、痛み、ストレス…。
どの噛み方にも、その子なりの理由や気持ちが隠れています。
それを知ろうとすることが、優しい飼い主さんへの第一歩です。
正しく理解して、愛犬との暮らしをもっと心地よく
噛む行動をただ「悪いこと」として叱るのではなく、「どうしてそうしたのかな?」と考えてあげることで、愛犬との関係はきっと今よりもっと穏やかで、あたたかいものになっていきます。
今日から少しだけ視点を変えて、噛む行動の奥にある愛犬の気持ちに耳を傾けてみてくださいね。
注意
他人を噛んでしまうと、健康保険の適用はなくて掛かった治療費は10割飼い主が負担することになります。
ライター紹介 Writer introduction
いずもいぬ
管理人:いずもいぬ(五十代前半) 家 族:子供1人とワンコの4人家族 居住地:大阪の出身で東京生活を踏まえ、現在は山陰で田舎暮らしをしています。 犬の健康管理や躾について、愛犬のラブラドールレトリバーとの経験を交えてご紹介しているホームページになります。